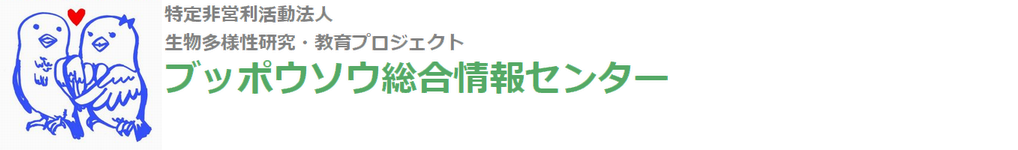2025年7月28日(月)
2025年7月の鳩間島
私は,今まで西表島には何十回も訪れ,主に島の西側と北側の海岸で調査を行ってきた。私の研究はフィールド・ワークを基礎として生物の形態・生態・行動に携わっており,研修届や出張届を大学に提出すれば,長期の研修や出張ができる立場にあった。
私の研究は,潮間帯(intertidal zone)の生物を対象としているため,琉球列島には大潮(spring tides)(干潮時には潮が一番よく引き,逆に満潮時には一番潮位が高くなる期間)の時期に合わせて訪れた。1か月に2回ある大潮の期間をフルに使うと琉大熱研に滞在する期間は20日を越えてしまい,授業の休講は3回になる。休講が3回になると補講が難しくなるので,滞在期間は2週間前後になることが多かったように思う。国立大学の場合には野外研究に対する理解があったが,私立大学の場合には野外研究というと,西表島に観光に行くとしか思っていない輩(特に医歯薬系出身の連中)が多い。私立大学ではもう講義はやりたくない。
鳩間島は西表島の上原からわずか6 kmほど北にある。宮古島と同じく,サンゴ礁原(reef flat)が隆起してできた島と思う。島全体が石灰岩に覆われていて,いわゆる「土壌」(soil)はほとんどない。島の最高標高は鳩間中森の30.1mである。見晴らし台に立つと,島の北側の海岸がよく見える。鳩間島に水道が通ったのは,1980年(昭和55年)のこと。水は,西表島の浦内川から海底を通って鳩間島に供給されている。それまでは島内3か所の井戸に加え,各家庭で雨水をためて使っていたのだろう。
鳩間島の海岸はサンゴ礁原(reef flat)になっている。しかし,西表島西部のように泥干潟(mud tidal-flat)はない。採集できる海産無脊椎動物が限られるために,しり込みをする年が続いた。一方,数年前からヤドカリ類を中心にして中生代(Mesozoic era)における十脚甲殻類の鋏脚(cheliped)の左右非対称の発現機構と進化の研究を始めた。ヤシガニの鋏脚は左右非対称で,どの個体も右側の鋏(minor chela)に比べて左側の鋏(major chela)が著しく大きく,物をはさむ力も半端なく強い。ヤシガニの祖先は,ジュラ紀にサンゴ礁原に出現したアナエビ(Archaeoaxius spp.)かもしれない。サンゴ礁原での堅物食(durophagy)が成功し,潮間帯ではカニ類を生み出す一方,陸上に進出して(定向進化により)体が大型化してヤシガニ(coconut crab)が誕生したのだろう。
鳩間島には,1回目は2024年(令和6年)6月30日だった。今回は2度目で,2025年(令和7年)7月6日(日)に訪れた。

図1. 上原港から鳩間島往復。西表島での調査・研究は,いつも琉球大学熱帯生物圏研究センター・西表研究施設(琉大熱研)に滞在して行われる。調査・研究は,毎日の潮(tide)の状態を考慮して行われることに加え,採集した海産生物のサンプルを固定するためにエタノールが使用される。採集するための器具やサンプルを収納するプラスチック容器,双眼実体顕微鏡(binocular microscope),顕微鏡撮影装置,接写用のレンズとカメラ等はすべて岡山から送られる。海産生物の採集とアルコール固定だけなら,民宿やホテルに滞在して行えるが,研究となると特別な施設(例えば臨海実験所)の利用が不可欠である。幸いにして西表島には琉球大学の教育・研究施設があり,長期間滞在して研究を行うことができる。また,西表島の西側から北側の海岸にはマングローブと泥干潟や砂干潟が続き,私の研究テーマである無脊椎動物(甲殻類)の進化の研究に好適な環境が広がっている。東海岸の干潟は琉球石灰岩(サンゴの死骸)でできていて,砂岩や泥岩は少ない。

図2.高速船から見た鳩間島の全景。非常にフラットな島であることがわかるだろう。最高峰は鳩間中森(ハトマナカムルと発音するのだろうか?)の丘で,海抜30.1メートル。八重山諸島は隆起した大陸プレートの境界にあるため,島々の周囲は浅海になっている。グアムのような絶海の孤島に比べて,波は穏やかである。

図3.大原港から石垣港に向かう高速船から見た西表島。西表島の最高標高は古見岳の469.5mだが,島全体に300mから400mの高さの山々が連なっている。そのため島の周囲には急峻な崖(砂岩)が張り巡らされている。正面に見えるのは仲間川河口にかかる仲間橋。西表島では山の中に入る道は限られている。

図4.鳩間島の海岸沿いの小道。道の両側には去年も今年もランタナの花が咲いていた。昨年(2024)はミニトマトがたくさん実をつけていたが,今年(2025)は全く見られなかった。放し飼いにされているヤギどもが全部食べてしまったのだろう。道にはヤギのウンチがいっぱい落ちていた。道の両側には,オオハマボウ,アダン(タコノキ),モクマオウ,センダン,アカギ,タブ,ハスノハギリが見られる。沖縄本島の海岸沿いを埋め尽くすギンネムは,鳩間島では少ない。

図5.鳩間島の丘に咲くランタナ(野生種?)。ランタナはホームセンターで購入できるが,ピンク色の品種は売っていないかもしれない。

図6.鳩間島の丘や海岸に自生するソテツ(裸子植物)。中央の黄色い塊は雌花と思われる。胚珠(大胞子葉?)は,多数の若葉様の花弁(?)の中に収納されているのだろうか?秋になると雌花の中に多数の実ができる。ソテツの実は有毒(毒の種類は不明)だが,煮れば食べられる。ソテツは,中生代のジュラ紀初頭に地球上に現れたようだ。ジュラ紀と言えば,ヤシガニの祖先がサンゴ礁原から陸に上がったころでもある。その意味では,鳩間島は,中生代の面影が強く残る島と言える。なお,ランタナを始めとした多くの被子植物(angiosperms)は,6500万年前の新生代に入ってから地球上に現れた。

図7.島の中央を抜けて北側海岸に出る小道。道端にあるイネ科の雑草(これは被子植物)は,ツノアイアシ(インド原産の帰化植物)かも知れないが,名前まではわからない。ススキではない。雑草の奥にはアダン(タコノキ)の群落があり,中に入って行くとヤシガニを見ることができる。鳩間島にはヒゼンダニは少なそうである。

図8.アダンの幹にとまるキジバトのペア。首の白黒の縞模様に違いがあるので,どちらかがオスで,どちらかがメスなのだろう。シジュウカラやスズメの黒い「ネクタイ」もオスとメスで模様は異なっている。ブッポウソウも首の前面にある青いマークが雌雄で異なる。キジバトはペアで行動するがアオバトは集団で行動する。

図9.タコノキ(アダン)の群落。道の縁で伐採してあるところからは,中に入りやすい。ヤシガニは,陸上に住む十脚甲殻類の中では最強の生物である。カニ類ではマングローブに生息するノコギリガザミが最強だが,人が近づくと逃げる。しかし,ヤシガニは人がジャングルに入ってくると,逃げるどころかじっとこちらを見ている。アダンのジャングルの中では逃げ隠れする必要はなく,エサが来たと思っているのかも知れない。ただし,ヤシガニの捕獲は大変危険な作業になる。

図10.アダンのジャングルの中で捕獲したヤシガニ。鋏(chela)の力はものすごく強いので,うっかり挟まれたら大変な目に合う。特にヤシガニは左利き(left handedness)なので,左の鋏(はさみ)は超危険である。右の鋏も力強い。私の予想では,ヤシガニは,20年から30年ぐらいは生きる。鳩間島のヤシガニは早く天然記念物に指定したらどうか?採集して生計を立てている者がいるからとの言い訳を聞くが,どっかの国から販売目的で捕獲に来られたらあっという間に絶滅する。その意味では,オカヤドカリ類を早くから天然記念物に指定したのは,自然保護のためには良い判断だったと思う。なお,ヤシガニはオカヤドカリの仲間ではない。

図11.フトボナガボソウの花にとまるリュウキュウアサギマダラ(マダラチョウ科)。フトボナガボソウは熱帯アメリカ原産のクマツヅラ科の多年生草本である。チョウは野に咲く花を見分ける特殊な能力を持っていると思われる。どうやって葉と見分けるのか?色がわかるのだろうか?複眼の中に,花の色や形に強く反応する視細胞があるのだろう。細胞,特にニューロンは見た目(微細構造)は同じでも,実際には異なった機能を有していると思われる。ヒトの脳のニューロンも同様だろう。

図12.ヤエヤマムラサキ(タテハチョウ科)のオス。ヤエヤマムラサキは,昨年(2024)は少なかったが,今年(2025)は多くみられた。天気が悪かったこともあり,動きは大変鈍く,花にとまっても翅(はね)は閉じてしまうことが多かった。ずっと待っても翅を広げてくれないので,指でお尻をつついてみた。昆虫類(Insecta)と甲殻類(Crustacea)は,節足動物門(Phylum Arthropoda)に属する。昆虫類は翅を含めて完全な左右対称になっているが,無脊椎動物の進化の頂点に立つ十脚甲殻類(Decapoda)・抱卵亜目(Pleocyemata)では,付属肢の分業化が進み,左右非対称になっている種類が多い。私の研究テーマは,抱卵亜目(カニとかヤドカリ)の十脚甲殻類における鋏脚左右性(heterochely)の発現機構である。十脚甲殻類の鋏脚左右性の確立過程は,十脚甲殻類の進化そのものと言える。

図13.モクマオウの幹にとまるヤエヤマムラサキのメス。ヤエヤマムラサキは,南方の島々(マリアナ諸島,台湾,フィリッピンあたりか?)から迷蝶として先島諸島にやってきて,現在では定着している。島々によって翅の模様が異なる。図13の個体は,後翅の白紋がよく発達している。現代進化学では「亜種」(subspecies)は死語になっているかも知れないが,どこの島からやってきた地域個体群かは不明である。形態だけから見て何種類の亜種が存在するかという議論は,趣味や生態学の世界なら通用するかもしれないが,自然科学としての現代進化学という観点からは,とっくに時代遅れになっている。

図14.島の北側に向かう小道。鳩間島には,泥岩や砂岩という土壌のもとになる岩石はほとんどなく,地面を掘ると死んだサンゴ塊(琉球石灰岩)が出てくる。(鳩間中森の中央部には,わずかに砂礫層が露出している。)水はけがよいため,島には池がない。島にあった3つの井戸も,真水とは言えず,かなりの塩分が含まれていただろう。にもかかわらず,道の両側には草木が生い茂る原因は,降水量が多いためだろう。7月6日は朝から曇っており,14時ごろから本降りの雨になった。

図15.道にでてきたムラサキオカヤドカリのメス。十脚甲殻類(decapod crustaceans)の中で,クルマエビの仲間だけは根鰓亜目(Dendrobranchiata)に分類されるが,その他多くの種類は抱卵亜目(Pleocyemata)に属する。抱卵亜目の十脚類(カニ,ヤドカリ,イセエビ,ザリガニなど)は,メスの腹部に卵(正確には胚)をくっつけて移動できるために,地球上の多様な環境に進出することができた。多様な環境へ進出することにともない,形態(morphology)も著しく多様化した。形態の多様化と機能の分業化は,胸部付属肢において特に進んでいる。胸部付属肢は3対の顎脚(maxillipeds)と5対の歩脚(pereiopods)に分化し,さらに第一歩脚は鋏脚(cheliped)となって捕食,防御,求愛行動などに使われている。昆虫類には見られない特徴として,抱卵亜目の十脚類では異鋏性(heterochely)が発達していることである。体節性の獲得と付属肢の機能分化は,甲殻類の進化の過程を強く反映している。なお,琉球列島に分布するオカヤドカリ類(6種類?)はすべて天然記念物に指定されており,捕獲するには文化庁の許可が必要である。サンゴ礁原の潮間帯に生息するサンゴヤドカリの仲間は捕獲許可がなくても採集できる。

図16.鳩間島の北側の海岸。先島諸島の海岸(サンゴ礁原)は,干潮時(low tide)には波がなく,遠浅のこともあって家族で遊ぶ(泳ぐ)には適している。しかし,潮が上げてくると波が出てくる。遠浅と言っても,砂浜から10mも泳げば足は底につかなくなり,子供を泳がせるには危険な状態に早変わりする。旅行の日程ばかり気にしていると大変な目に合うので,海で遊ぶときには前もって潮汐表(tide table)をよく見ておく必要がある。

図17.鳩間島の西側の海岸。正面に見えるのは西表島。星砂の浜(住吉)あたりが見えている。天気が悪いのと潮が上げているので,波が出ている。海がこのような状態になると,小さい子供を連れて遊ぶのはまずい。現にこの時間には誰も泳いでいなかった。鳩間島と西表島の間の海は天気が悪くなるとすぐに波が高くなる。

図18.海岸に打ち上げられたプラスチックごみ。地球上に働くコリオリの力により,北半球の海洋では右回りの海流が発生する。赤道のすぐ北には,赤道に沿って西に向かう海流がある。この海流(黒潮)は,フィリッピンの沖合(フィリッピン海)で北上し,日本列島に達する。先島諸島の海岸に漂着したプラスチックごみ(ペットボトルが多い)は,日本では製造されていない種類が目立つ。また,中国語が表示されたボトルも多い。中国東南部や台湾で投棄されたゴミが流れ着いたのだろう。

図19.海岸に漂着したプラスチックごみ。砂浜で清掃作業をしている家族に会った。家族で鳩間島に来て,両親が鳩間小中学校の教員か職員をしていると予想した。あるいは郵便局の職員とその家族かも知れない。漁師,民宿,公民館の関係者ではないと思う。鳩間中森にある友利御嶽では,参道の掃除をしている若者に出会った。時々東京や大阪に出かけて仕事をして,鳩間島に戻ってきて過ごしているという。集落の中に漂着した「浮き」に描いた顔の絵を石垣の上に並べてある家があり,彼はそこに住んでいるようだ。鳩間島には夏は観光客が多く訪れるが,冬場になると島は閑散としていると言っていた。

図20.島の北側の空き地に置かれた燃えないゴミ。鳩間島では,燃えないごみを処理できる施設はない。(島の中央部に一時保管するところはある。)廃棄モーターボートが10個も並ぼうものなら,「燃えないゴミの島」と化すだろう。島のインフラ整備が進むほど燃えないゴミの量は増加する。

図21.島の北にある空き地に捨てられたモーターボート。エンジンがかからなくなっているか,操舵機能が壊れているのだろう。電気製品や小型船舶の修理や解体を引き受けてくれる専門の工場は,石垣島にしかない。新品なら貨客船「かりゆし平成丸」や「カーフェリーぱいかじ」で運んでくれるだろうが,産業廃棄物は運んでくれないだろう。鳩間島は,カツオ漁が盛んな時期(明治と大正)には人口は700人に達したこともある。その時代にはゴミが大量に出ただろうが,多くは燃えるゴミだったと思われる。(しかし,633mlのビール瓶は島のあちこちに転がっている。西表島の白浜でもたくさん見た。) 島のインフラが整備されてくれば,人口は増加することが予想されるが,生活に使われる電化製品や小型船舶などの廃棄物が急増して,ゴミの島になることは目に見えている。

図22.石垣港。小型船舶の解体場は,橋を渡って右側の人工島(写真には入っていない。)にあるが,解体作業が積極的に行われているという印象は受けない。正面の岸壁に停泊中の船は,フェリー「よなぐに」。右側は,黒島あたりから石垣港に向かう高速船。なお,西表島の東部には,中底モータース(「西表レンタカー」会社も兼ねる)があり,車の修理を一手に引き受けているが,敷地に置いてある廃車の数は増加している。先島諸島の自然を守るためには,行政,特に竹富町の環境保全に関する部署(名称はわからない)の強力な指導が必要だろう。お涙頂戴的な住民の主張に負けたら,ゴミの島になるのは目に見えている。もうひとつは,職員に対して,自然保護の基本としてサンゴ礁原の形成機構とか,サンゴ礁原やマングローブを生活場所とする生物の進化とか,サンゴ礁生態系の基礎知識を教えたらよいと思う。数多く出版されている熱帯生物の紹介書とか,生態学のように「お話し」の学問ではなく,現代生物学の知見を基礎にした実証的科学の基礎を教えたらよい。物理学や化学の知識も重要である。高校の物理や化学が苦手ならば,大学に入ってから地球化学とか地球物理学を勉強すればよい。理系の教員は,専門教育科目の履修を早めろと声高に主張するが,それを認めると,学問に対する視野が狭まり,自分の都合しか考えられない「自己中」人間が街にあふれる。

図23.鳩間島のお花畑。武家屋敷跡地の道を挟んで反対側の緩斜面(10m×20m程度の面積)にある。種名はダールベルグデージーとかキダチハマグルマあたりと思うが,どちらも違っているかもしれない。(私は種名にはそんなにこだわらない。)鳩間島ができたのは,シャコガイの年代測定から,わずか2,600年前(2,600‘万’年前ではない)と推定されている。こんなに短い時間では,島にある植物はすべて外来種(帰化植物)になるだろう。なお,西表島は1,350万年前(新生代・新第3紀・中新世)である。全島300mから400mの山に囲まれた複雑な地形を有しており,いくらか固有種(endemic species)がいても不思議はない。

図24.赤色あるいは黄色の花弁のランタナ。真上から見た時には多くの花の形態(morphology)は放射相称が多い。一方,ユリは正面から見ると放射相称だが,横から見ると左右対称に近い形になっている。植物では,花びらの形や色を決める遺伝子はあるだろうが,左右対称の形態をもたらす遺伝子はないだろう。ここが動物と大きな違いである。左右対称の形態ができるためには,右と左の方向を知覚する神経細胞(neuron)が必要なのではないだろうか?

図25.琉球石灰岩の上にとまるアオタテハモドキのオス。昆虫類の形態は,左右相称(bilaterally symmetrical)になっている。形だけでなく前翅や後翅に現れる斑紋や模様も左右対称であるところが面白い。胸部に3対ある付属肢(appendage)もやはり左右対称である。一方,同じ節足動物門(Phylum Arthropoda)に属するカニやヤドカリの仲間はどうか?付属肢は鋏脚(cheliped)に変形している種類が多く,しかも右左の鋏脚の大きさと機能が異なる種類が多くなる。甲殻類における左右異形鋏脚(heterochely)の発現機構は,甲殻類の進化と密接に関係しており,現代生物学の重要な研究課題であると思う。Heterochelyの発現機構を比較すると,甲殻類と昆虫は,互いに違った方向に進化したことがわかる。進化の研究には,物理学や化学の知識が必要だが,生物多様性の知識も不可欠である。物理・化学・数学に精通している人たちが進化生物学の分野に関心が薄いのは,生物多様性に関する理解が乏しいからではないだろうか?一方,生物多様性に関心を持つ人たちは,技術(technology)の発達に背を向け,旧態依然とした古典分類学の世界(新種の記載)に閉じこもっている。私は,古い生物学の殻を脱ぎ捨てて戦いたい。

図26.公民館の玄関にあるシャコガイの化石(すでに石灰岩になっている)。子供がすっぽりと入ってしまうほどの大きさである。種名は不明。道路を作る際にブルドーザーで地面(サンゴ礁石灰岩)を掘っている時に出てきたか,海岸の琉球石灰岩の露頭の中に埋っていたのかも知れない。シャコガイの体の大きさにも定向進化が働いている可能性が高い。系統学者は生物の系統(phylogeny)について,口を開けばmonophyly(単系統)と言うが,定向進化(directed evolution)の証拠がなくしてmonophylyと断言することは難しいのではないか?現在十脚甲殻類(Pleocyemata)の進化を検証しているが,polyphylyと考えられる事例が割と出てくる。
<参考文献>
・Akam, M. (2000) Arthropods: developmental diversity with a (super) phylum. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97:.4438‒4441.
・Burggren, W.W., and B.R. McMahon. 1988. Biology of the Land Crabs. Cambridge University Press, Cambridge.
・Castro, P., and M.E. Huber. 2005. Marine Biology, Fifth Edition. McGraw-Hill Companies, Boston.
・Cook, C.E., M.L. Smith, M.J. Telford, A. Bastianello, and M. Akam (2001) Hox genes and the phylogeny of the arthropods. Curr. Biol. 11:759–763.
・Factor, J.R. (ed.) 1995. Biology of the Lobster: Homarus americanus. Academic Press, San Diego.
・Ferl, R.J., and R.A. Wallace. 1996. Biology: The Realm of Life, Third Edition. HarperCollins College Publishers,
・Futuyma, D. 1998.Evolutionary Biology, Third Edition. Sinauer Associates, Inc., Massachusetts.
・池田嘉平・稲葉明彦(編) 1971. 日本動物解剖図説。森北出版。
・仲里健 (2015)鳩間島・黒島・新城島(上地・下地)の地質。鳩間島・新城島・黒島総合調査報告書(沖縄県立博物館・美術館) 1‒12.
・Regier, J.C., and J.W. Shultz (1997) Molecular phylogeny of the major arthropod groups indicates polyphyly of crustaceans and a new hypothesis for the origin of hexapods. Mol. Biol. Evol. 14: 902‒913.
・山田真弓・西田誠・丸山工作. 1981. 進化系統学。裳華房。
・小竹信宏・亀尾浩司・奈良正和 (2013)沖縄県西表島の中部中新統西表層最上部の地質年代と堆積環境。地質学雑誌119: 701‒713.
・フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」 ソテツ。
・フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」 定向進化。
・Masunari N., K. Sekiné, B.J. Kang, Y. Takada, M. Hatakeyama, and M. Saigusa (2020) Ontogeny of cheliped laterality and mechanisms of reversal of handedness in the durophagous Gazami crab, Portunus trituberculatus. Biol. Bull. 238: 25‒40.
・Vermeij, G.J. 1987. Evolution and Escalation: An Ecological History of Life. Evolution and Escalation. Princeton University press, New Jersey.
<記事に関する基礎情報>
執筆:三枝誠行(NPO法人,生物多様性研究・教育プロジェクト常任理事)。
撮影機材:風景と生物の写真は,EOS 7D(レンズ: Tamron 28‒300mm, F/3.5‒6.3 Di VC PZD)で撮影。カメラ,レンズとも中古品を購入した。私の場合には,カメラの扱いは乱暴である。新品は高価なのでフィールドに持って行けない。硬いものにぶつかって故障したり,海水がかかって調子が悪くなったりしたら,修理するにしても,買い替えるにしても高額になる。EOS 7Dのような高級品を中古で非常に安く購入できるのは,大変ありがたい。