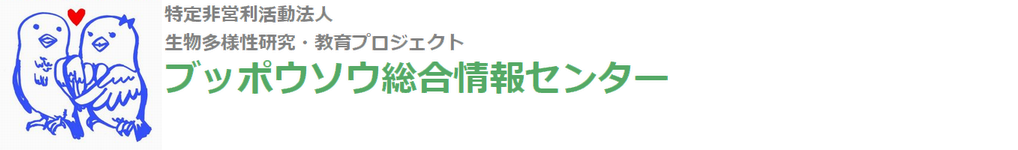多様性プロジェクトでは,新しい研究テーマ(いずれ公開される)が始動しています。新しい研究では,十脚甲殻類(エビやカニの仲間)が対象となり,研究に必要な十脚類を採集するために,毎週高知県に出かけています。
採集と言っても,土佐湾の刺網(さしあみ)と底引網(そこびきあみ)でとれたエビとカニを購入し,それらを冷凍,あるいはアルコール固定し,鋏肢(第1歩脚)の計測や抱卵システムの観察(SEMやTEM)を行っています。
研究の詳細は,論文の方に示すとして,多様性プロジェクトのホームページには,いま土佐湾でどんな十脚甲殻類が採集できているか,写真とともに(日本語で)紹介します。
11月には4回高知に行っています(7日,16~17日,22日と30日)。岡山に戻ってから,サンプルを仕分けし,種類を調べ,リストを作り,標本はアルコールで固定して保存という段取りです。
写真は,11月30日(土)に池ノ浦(須崎市)に行った時に撮影しています。
土佐湾(図1)は,地形的には駿河湾と似ていて,どちらも似たようなエビ・カニ類が生息しています。

11月30日は,刺網漁をしている小型船(図2)で採集された十脚類を購入しました。刺網ではいろいろな生物が採集されます(図3と4)。こういう獲物は市場には出されず,全部捨てられてしまいます。船が帰ってきた直後にもらって煮たり焼いたりして食べたら,おいしそうな種類が結構入っています。

ゾウリエビ,セミエビ,それにアサヒガニも獲れる。
サメはどうにもならないが,エイならばみそ汁に入れれば食べられそう・・・。しかし,アンモニアの臭いがきついかもしれない・・・。なお,写真(図3)の獲物はもう6時間ぐらいたっているので,腐り始めていると思います。

エイや結構大きい魚の他,カイメン,刺胞動物(ウミエラみたいな生物),棘皮動物(テズルモズルとかユウレイモズルとか・・・)に混じって,カニ類やヤドカリ類が引っかかる。

研究対象になっていない生物の分類(identification)には時間をかけられない。
文献は挙げないが,カニ類の起源はジュラ紀のようです。古い時代(白亜紀中期?)に祖先が出現した原ガニ類,続いて古ガニ類(白亜紀後期?),それに海岸や河口でごく普通にみられる新ガニ類(新生代)がいます。
土佐湾では原ガニ類も少しいますが,多いのは古ガニ類(図5)が非常に多く採集されるのが土佐湾の特徴です。(というか,初めて見る世界なのでそんな風に思えてしまう・・・。)

ケアシガニがいる。それと一番下(中央)のカニは,イソクズガニの1種だったか?
今まで原ガニ類や古ガニ類のいる生息場所を対象に研究したことがないので,採集されるサンプルをみると,その個性的な姿や色彩には本当に驚かされます。採集された標本の写真を撮っていると,まるで夢の中の世界にいるような気分になってきます。
で,今やっていることは,鋏脚(カニのツメがある歩脚:第1歩脚)の左右性の発現機構です。多くのカニ類では,鋏あしの大きさは左右対称です(ツノナガソデカラッパやカイメンガニ)。原ガニ類はみな左右対称ですね。古ガニ類は,左右対称の種類が圧倒的に多いのですが,カラッパの仲間(ファイルの添付ない)だけは,非対称です。新ガニ類になると,いろいろなタイプの左右非対称が出現しています。


異なっているのが分かる。カニ類の場合には,非対称は指節(dactylus)と
掌節(propodus)に発現している種類が多い。
なお,このカラッパ(図7)の種類は図鑑やインターネットを調べても出てこなかったので,ツノナガソデカラッパと名付けた。和名に関しては,検索に引っかからない種類については,特徴をよく表す(暫定的な)名称を付けたらよいであろう。そういうことでけんかをするのは時間の無駄である。
大事なのは,土佐湾の比較的浅い岩礁底(おそらく20mから50mぐらいの深さ)には,多くの古ガニ類(旧ガニ類)が生息しているということである。